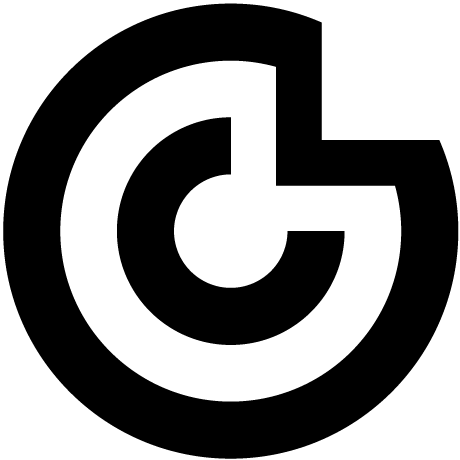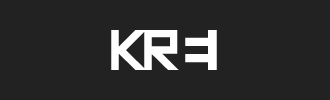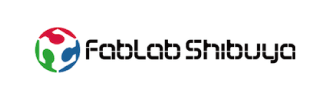![]() INTERVIEW
INTERVIEW
#12 kabuku / rinkak|稲田雅彦氏|CEO
稲田雅彦
Masahiko Inada
今回はco-lab渋谷アトリエの会員・kabukuの稲田さんにインタビューしています。kabukuは3Dプリンタを活用した、デジタルものづくりプラットフォーム「rinkak(リンカク)」を運営している会社で、稲田さんと日本に数人しかいないGoogle Expertでもあるというプログラマーの足立さんを中心に、エンジニア、アートディレクター、プロダクトデザイナーのメンバーで活動しています。広く、ウェブや紙のメディアで取り上げられているサービスなので、rinkakをご存知の方もいるのではないでしょうか?
そんなkabukuの稲田さんに、co-lab運営企画・田中からいくつかの質問をしました。そもそも、どうしてco-labを活動拠点として選んだのかという話にはじまり、パーソナルファブリケーションがものづくり文化を、そして日本をどう変えていくのかという話にまで広まった二人の対談をお届けします。
kabukuが目指す未来は、大人だけでなく子ども達にも新しいクリエイティブの機会をフラットに捧げるものでした。パーソナルファブリケーション、デジタルファブリケーション、今とこれからの物づくりに関心のある全てのクリエイターに、このインタビューを贈ります。
インタビュアー:田中陽明(co-lab運営企画)
構成:新井優佑(co-lab WEB PR)
――co-labに入ることを決めたキッカケは何ですか?
「多様な人が集まる場にいると大きな山に登れると思ったからです」
田中:ぼくと稲田さんの出会いは、稲田さんが博報堂に勤めていたときに開かれた博報堂グループの新規ベンチャー制度「AD+VENTURE」のコラボレーション相手としてco-labを利用してもらったことがキッカケでしたよね。博報堂20人:co-lab20人のお見合いみたいなことをして、ベンチャー企画を一緒に事業化するという。その後、kabukuはrinkakというWebプラットフォームを立ち上げて、それらの活動を拝見する中で、バーチャルや研究者という枠の中だけでなく、外との繋がりに重点を置いた活動をしている様子を感じていました。それはビットからアトムへ戻っていくことを強く意識されているからなのだろうと思っていて、きっと、co-labに入ろうと思ったキッカケにも繋がることなのでは、と思うのですがいかがですか?
 →rinkak | 3Dプリンター・3Dプリントのものづくり&マーケットプレイス
→rinkak | 3Dプリンター・3Dプリントのものづくり&マーケットプレイス
稲田:それこそ、co-labを知ったキッカケは博報堂時代に新規ベンチャ制度「AD+VENTURE」に、運営としてぼくが関わっていたことです。このプロジェクトでは既に6社立ち上がっていまして、このプロジェクトのマネジメント、ハンズオンのサポートをしていたのですが、いざ独立するというときに、「オフィスをどうしようか」という話になって、単独で部屋を借りることも考えていました。でも個室を借りると、固定費の負担が重なってしまうので、それならば今はコ・ワーキングだろうと思ったんですね。コ・ワーキングをざっと調べてみたのですが、最近はIT色が強いところが主流で、そういう場に入ったとしても、異質な物が得られず、化学反応はおきないなと。それで、自分たちよりも上の世代や全く異なる人たちと同じ空間にいないと、刺激が得られないんじゃないかと思ったんです。それで異質な人が多くいるところに入りたいなと思って、co-labを選びました。ビットなのかアトムなのか、あるいはビジネスなのかアカデミックなのか、ということではなく、ぼくらは多様性を大事にしています。自分たち自身だけでなく、ふだん付き合う人も多様でなければ、小っちゃい山を登ってしまうと思っているんです。ぼくらはよく、小さな山か大きな山かという話をするんですね。大きな山を登るには、優秀でも均一的な人が5人集まることよりも、バラバラでもユニークな視野があったり、アイデアが優れている人、というように多様な人間が集まったほうが最終的に大きな山に登れているということがあると思うんです。
田中:なるほど。同感です。
稲田:もともと人工知能の研究をしていて、その話ではあるのですが、多様性のあるほうが最終的に大きな問題を解決できることがありまして、それを比喩として、多様性のあるほうが大きな山を登れると思っています。同じように、尖った人ばかりが集まってしまうと、小さな山を登ってしまっていても、気づかないことがあるんです。優秀であるが故に、変な方向に行ってしまう例も過去には多くあったと思います。だから敢えて多様性のあるところに突っ込んで行ったほうが確実に面白いなと思っていました。
田中:kabukuの利用するco-lab渋谷アトリエ1階には、そういう意味では一番多様性のあるco-labらしいメンバーが同居していますよね。
稲田:アカデミックかビジネスかという話でも、研究者上がりの多いぼくらだけではダメなんです。今、kabukuにフルコミットしている面々は4名で、それ以外に10数名の方にサポートして頂いており、デザイナーやハードウェアのエンジニア、キュレーター、ソフトウェアのエンジニア、コピーライターもいる中で活動しています。それもやっぱり多様性に重点を置いているからなんです。あとは、やっぱりビットだけ、ITだけで完結できる時代じゃないので、物も含めて、フラットに情報データを扱って大事にされる物を作ろうと思っています。Webサービスだろうが、電気製品だろうが、コップだろうが、本質的に大事な物を作って行きたいと思い、独立しました。
――渋谷アトリエで他のメンバーとの交流はありますか?
「実際に物を作る機微などを知ることができ、刺激的です」
田中:以前、拝見した稲田さんのインタビュー記事では、初音ミクのリアル版、モノ版を意識しているという話を目にしました。まさにそれですね。
稲田:リミックスの考え方ですね。初音ミクってデータや音楽、コピー映像、フィギュアを含めてニコニコ動画を通じてリミックスされている。その場の中で、たまたま初音ミクがアイコン化して、うまく普及していったと思うんです。新しいデジタルファブリケーションの世界では、アイコンとして、何が適したものなのかはまだ見つかっていないんですが、モノのリミックスみたいなことも、もともとデータとビットの世界から始まったオープンな考え方で捉えて、自分たちが自然にやってきたことなので、WEBに自然な方々にとっては、自然にやっていけると考えています。10年以上前からパソコン1台あればWebサービスが作れて、アプリも、映像も、音楽も作れる。それがぼくたちにとっては自然。でも物になるとデータを作っても工場を口説かなければいけないし、金型を起こして、量産してというような作業があって、まだまだ物の世界では、すごく高いハードルがあると思います。ソフトウェアの人間が物づくりの中に入っていき、フラットにパソコン1台で作ることのできる世界になると、それこそ日本のものづくりの世界も変わるはずで、そのキッカケとしてrinkakをやっているんです。
田中:物づくりを始めると、意外と難しいこともありますよね。co-factoryのような工房や、運営スタッフの山元さんやFabLab Shibuyaのような人がいる渋谷アトリエであれば、物化するときのサポート体制もあるので、役立ったりするんじゃないかなと思っています。
稲田:元々、足立は機械工学科の出身なのでファブリケーションについてはかなり知っているんですね。ただ、本当の現場でどうするかという面ではまだまだ知らない部分も多く、そういう意味で立ち話ベースでも教えてもらえるのはものすごく有難いです。
田中:渋谷アトリエメンバーとも3Dプリンタのディスカッションをしている様子を拝見していました。密なやり取りをしているな、と思っていたんです。売れる物を作って来た人が渋谷アトリエにはいて、そういうメンバーとの交流の中で参考になることもありますか?
稲田:量産目線で考えたり、実際に物を作る機微などを知れることはものすごい大事で、刺激的です。年配の方でも、畑の違う人でも、とてもフラットに会話できています。逆に、ビットからアトムに来るとき意識せずに考えていたことがそのままできちゃったりするので、物の人からするとそれを新鮮に感じてもらえているとも思うんです。だからこそフラットで、「こんなことはできないか」「なるほど、なるほど」という感じのコミュニケーションが取れています。そもそも、プログラムから自動で作り上げるなんて、昔はできなかったことなのでそれはそれで面白いなと。
――パーソナルファブリケーションが生む新たな体感は?
「例えばディスプレイから取り出す瞬間の“WOW!”ですね」
田中:パーソナルファブリケーションが今までのものづくりに与える新しい体感はありますか?
稲田:CGで作っていた人からしたら、ディスプレイから物が出て来たという感覚を得られること自体、「WOW!」があると思います。でもリアルの物を作ってきた方には当たり前なのでそこには「WOW!」がない。その「WOW!」があるから作ってみるんですが、ディスプレイから取り出そうとしたときに、完全には取り出せない状況があって、そこの技術革新が起こりはじめています。厚みや尖り、素材の重要性はディスプレイから取り出して初めて気づくこと。尖りすぎていると折れちゃうとか、厚みが薄いと破れるとか、素材の選定を間違えると食器にならないとか。今は、そういう時期なんです。
田中:建築でCGを扱っていた人は、まさに取り出せるCGを作ってきました。でもイラストレーターやアニメーターからしたら、はじめての体験で、よく見たら線が繋がっていない、なんていう経験もあるでしょうね。
稲田:ソフトウェアも最初は全然こなれていないし、自動でものを作るにしても、例えばこのコップ自体、実際は底の部分に溝をつけないと立たなかったりするんですね。あと、このコップで水を飲もうとしたら厚みがありすぎて横からこぼれてしまったりもします。そういう課題が、作ってみてはじめて見えて来て、ソフトウェア自体もそれをチェックできるように作りかえていけば、ちゃんとした物が作れるようになる。そういう工程は、やっぱり職人の世界なんですよ。ハードでもソフトでも一緒で、ソフトウェアの中にも職人の世界があります。例えばWebサイトやアプリを作る場合にしても、最初はドラフトを手描きで作るんですね。使い勝手等を手で確認して、試してから作る。これはアメリカ・シリコンバレーをはじめとする西海岸でも主流のやり方です。メモを取りながら考えて、デザイナーに起こしてもらい、動くようにして、また手でいじるということを繰り返す。そのプロセスはアナログそのもので、リアルの物づくりをして来た人と通じる部分で、同じ精神がそこにあると思います。パソコンで物づくりができる状況を作ると、今までと異なるやり方をして、何も考えずに完成させてしまう人もいるとは思うんですが、失敗するんですよ、どっちみち。人の目は肥えているので、結局ダメだということがわかって、じゃあ、どうするかを試行錯誤する。それは職人の世界です。
田中:rinkakでは補正作業をしたりはしますか? 人が中に入って、精査するのでしょうか。
――デジタルファブリケーションが産み出す新たな価値は?
「例えば職人の勘に頼ってきた部分を“見える”ようにできます」
稲田:簡単なチェックはシステムが行います。データとして送られてきたものを自動でチェックするんです。システムがものづくりをサポートできる領域が増えていて、強度計算や、物体が立つか立たないかなどのシミュレーションはシステム側で行うことができたり、今まで職人の勘を頼りにしていた面がどんどんとデータでも見えるようになってきていると思います。
田中:そもそも、このrinkakやシステム自体を開発したのがkabukuなんですよね?
稲田:そうです。小さなチームですが内製です。ぼくらのメイン事業はrinkakですが、それ以外にも自分たちで物を作ることも予定しています。
田中:今現在、rinkakの収益モデルはどうなっていますか?
稲田:CtoC(Consumer to Consumer)で、一般ユーザーでもありクリエイターでもある出品者から、出品した物を買ってもらったときにシステム利用料を頂いています。Yahoo!オークションやアプリのマーケットと同じモデルです。
田中:今後、FabLabとコラボレーションしていく可能性はありますか?
稲田:FabLabさんは教育に重点を置かれていて、ぜひそこでもご一緒させて頂ければと思います。パーソナルファブリケーション自体が広まらないとぼくらとしても生きていけないので、一般の方を含めて、Jリーグやメジャーリーグを作るように、裾野を広げて、小学生や幼稚園児がサッカーができるようにしていきたいです。裾野が広がることで、トップの人のレベルも高まると思います。ソフトウェアの世界でも、小学生にまで裾野が広がり、トップ層のレベルも高まることで、日本のプログラマーの世界は世界で活躍レベルの方がごろごろいます。この前、お子さんでも使えるアプリを作ったんですけど、それで何かコラボレーションできないかっていう話とかをしています。(アプリ「ボクスケ」の動画を参照しながら、)CADソフトとは違って、子どもでも簡単に作れるような物にしようという話で作りました。小学3年生くらいまでは立体の把握力が低いという話があるので、3D自体がなかなかできなく、だからこれはほぼ2Dのお絵描きアプリなんですね。それを通して、まずはパーソナルファブリケーションの世界に片足だけ踏み込んでもらって、また違うワンステップを踏めるようにしていくことで、どんどん裾野が拡がっていくんじゃないかと思っています。
https://youtube.com/watch?v=qbbZIP0Io7k%3Frel%3D0%22+frameborder%3D%220%22+allowfullscreen%3E%3C
――これからの物づくりに必要な人は?
「ハードとソフトの両面を理解して、いろんなものを紡ぐことができる人」
田中:確かに、子ども向けの3Dモデリングソフトはありませんし、それで作ったおもちゃも見たことがありません。自分が描いた物が立体として浮かび上がってきて手で持てたら驚くでしょうね。
稲田:それは粘土でもいいんです。アプリのほうが気楽ならそれでもよくて、やっていることは一緒だと思っています。
田中:でも粘土はそこにあるものを練り上げていくわけですよ。それが画面上にある物がボコッと出てくるという違いはあるように思いますよ。
稲田:今の時代はどちらもあるのが面白いと思います。
田中:ドラえもんの世界に近い感じがしますね。漫画の世界にしかなかったことが、そこまで近づいてきていて、面白いです。
稲田:ぼくたちは3Dプリンタネイティブではないので、わからない部分ではありますね。
田中:そうか、子どもの頃から使っていたら、確かにネイティブですよね。
稲田:今、電子書籍を使っていても、もともと紙で読んでいたわけじゃないですか。捲るときにペラッとなりますけど、でもたぶん、ペラッと捲れる必要ってないんじゃないかと思うんです。小っちゃい子が最初からiPadで始まって、ペラッって何だろうと思っていて、あるとき、週刊少年ジャンプを紙で買ってみて初めて、ペラッってこういうことだったのかと気づいたりするかもしれません。
田中:なるほど、あとから付いてくるわけですね。
稲田:音楽も、iTunesでダウンロードしてPCで電子データを受け取って聞いていますし、CDだってレコードと違って溝がないわけで、それぞれ違っていてもそれが普通なんです。ぼくはDJを始めて初めてレコードを買いました。そこで初めてレコードの良さはレコードにしかないということがわかりましたし、そういう逆の順番で知っていく流れと同じかなと思っています。
田中:kabukuには稲田さんだけでなく、足立さんというすごいエンジニアがいますよね。プログラムの世界はあまりよくわからないので、すごいんだという認識しかないのがあれではあるのですが。
稲田:渋谷アトリエにはすごい方がたくさんいらっしゃいますから、異なる分野のすごい人たちと混じり合いが生まれれば、日本を変えられるんじゃないかって思っています。
田中:そうですよ。そこをうまく繋いでいく立場なんですが、それぞれの人の領域がとても尖ってきていて、そのトップを行く人たちの間を繋ぐとなるとすぐには理解できない、把握できないことがあるなと思っています。
稲田:そうですよね。繋ぐことのできるコーディネーター含め、今の日本は繋ぐ人が少ないと思います。ハードとソフトの両面を分かっている方もかなり少ないです。
田中:海外で言うとジェネレーターですね。ちゃんとしたポジションが確立されていて、日本で言えばコーディネーターやキュレーターということなのでしょうが、まだよくわからない存在というふうになってしまっています。ぼく自身、co-labというプラットフォームを運営していて、稲田さんはrinkakというプラットフォームを運営する人で、rinkakでは稲田さんがアウトプットにおける細かい点のフォローをしているわけじゃないですか。それを物理的な場に広げて、バーチャルとリアルを繋ぐことのできる、両方の共通言語を理解している人となると少なくて、さらに販売のことまで考えられる人となるともういないのが現実ですよね。それはもうぼく自身も一人でやっていけることではなくて、各メンバーが自身の領域を研ぎすませている中で、領域横断的にやっていきたい人同士が集まって、知識を高め合ったりしていったほうがいいんだろうと思っています。そういう場合、企業や研究活動で行うよりも、co-labのような場のほうが何か起こると思っているんですね。
稲田:MIT(マサチューセッツ工科大学)のメディアラボが昔、違う領域の人を20人集めて、そこに課題を一つ出すということをやったら2時間で今まで出なかった答えが見えた話があります。同じ山を登っている人達からしたら高く見える山でも、全然違う山を登っている人から見たら別のルートがわかることって結構あると思います。それと同じで、同じ会社で頑張っていても登れる山はたかが知れていて、違う山を登っている人とああだこうだしたほうが高い山に登れるという。でも、そのときに登り方を知らないとケンカになるので、そこだけはケンカしないでおこうというようなことさえ決めていければ……それってどうやったらできるんでしょうね。
(最後に)
パソコン1台でリアルの物づくりを行える世界は、未来の話ではなく、今現実に普及しはじめている世界です。ビットからアトムへ、またはアトムからビットへではなく、アナログとデジタルの物づくりが交差する現代、その最前線が語られた今回の対談は実にスリリングで、「どんな物づくりができるようになったのか」と好奇心が沸いた方も多いのではないでしょうか?
そんな全てのクリエイターが抱く好奇心が、未来のクリエイティブを育てる礎になることも、今回の対談で感じることができました。将来、小ロットでの物づくりが一般的になった際、今まで物づくりの伝統を担って来た方々と新しく物づくりの世界に入って来た人たちを繋ぐことこそ、co-labの果たす役目の一つなのかもしれません。
デジタルファブリケーション工房「co-factory」の併設する渋谷アトリエでは、日々、その最前線を肌で感じながら物づくりに没頭することができています。現場から得られた生の体感をどうフィードバックしていくか。co-labの挑戦は尽きません。kabukuのような刺激を与えてくれるメンバーと一緒に、これからの物づくり文化を育てていきたいと思っています。